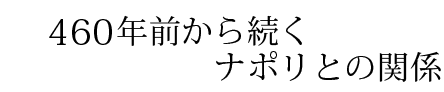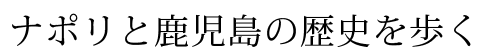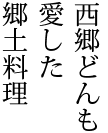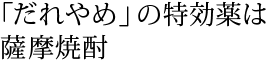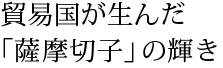幕末に世界に向けた輸出品として製造された「薩摩切子」。ガラスに色ガラスを被せ薄くカットしていく独特の技法でつくられ、鮮やかな色彩を放つ。明治時代に入ると事業は途絶えたが、昭和60年に復元。以後、鹿児島を代表する工芸品として知られている。

ベルナルド(左・真ん中の銅像)からはじまった鹿児島とナポリの関係は、4世紀の時を経て姉妹都市の盟約を結ぶまでに至った。盟約を記念し、両市民がナポリ通りをパレードした50年前(右上)。市の国際交流事業「青少年の翼」では、毎年10名ほどがナポリを訪問(右下)。

仙巌園に隣接する「尚古集成館」は、島津斉彬が近代化のための事業を行った工場跡地。ここで造船や造砲などの軍事から、硝子や印刷などの産業まで、明治に先駆けて幅広く富国強兵策が推し進められた。
同館は島津家の歴史・文化に関する展示と当時つくられた反射炉の模型などが飾られており、斉彬や薩摩藩士の息吹を感じることができる。国の重要文化財である慶応元年(1865)に竣工した機械工場を本館として利用している。鹿児島でも随一の観光スポットだ。
鹿児島市とナポリ市が姉妹都市となって50年。だが、その深い絆のルーツは、それよりさらに4世紀も前にさかのぼる。
約460年前、この地でキリスト教の布教を始めたフランシスコ・ザビエルから最初に洗礼を受けたベルナルドという鹿児島出身の青年がいた。やがて彼はヨーロッパへ旅立ち、日本人ではじめてローマ教皇に謁見する栄誉に恵まれる。そしてその旅路の途中、立ち寄ったのがナポリだ。彼はきっと、ベスビオ火山を見たことだろう。過酷な旅で出会った故郷の桜島とうりふたつの山を擁する光景は、彼にどのような思いを抱かせただろうか。鹿児島市内のザビエル公園にあるベルナルドの銅像を見て、そんなことを思う。確かなのは、鹿児島とナポリの関係は彼からはじまり、今、さらに深まっているということだ。
ところで、鹿児島はナポリやキリスト教に対してだけでなく、ほかの地域の人や文化との接し方が柔らかい。今回の旅でも、お店や通りがかりの人々が積極的に話しかけてきてくれた。
「薩摩は、海洋国家として日本でも屈指の貿易国でした。南は琉球、西は中国、そしてはるかかなたのヨーロッパまで、あらゆる国の玄関口となっていたので、自然とおもてなしの心が根付いたのでしょうね。何しろ殿様が誰よりも開明的でしたから」と、仙巌園の人がその理由を教えてくれた。仙巌園は現在の鹿児島全域を含む、薩摩藩を代々統治してきた島津家が、江戸時代初期に築園した広大な日本庭園。四季折々の表情と錦江湾と桜島を望む景勝の地で、国内外から多くの観光客を集める。
仙巌園に隣接する「尚古集成館」は、幕末の名君・島津斉彬(なりあきら)が、欧州の列強国を意識し、富国強兵を目的に建設した機械工場群だ。美しい輝きを放つガラス工芸品の「薩摩切子」は、海外で売れる製品を目指し、細やかな日本の技術を生かしてここでつくられていたという。
多くの異文化と接する薩摩では、技術だけではなく食も独自の発展を遂げた。たとえば、「トンコツ」などに代表される郷土料理ではよく豚肉が使われている。本州では仏教・神道の影響で獣肉食はタブーとされてきたが、中国や琉球の食文化の影響下にあったため、薩摩では肉は公然と食されており、豚肉を含む豊富な食材を薩摩流にアレンジしていったのだそうだ。薩摩流とは? と郷土料理店で聞いてみると「焼酎に合うかどうか」と即答。冗談半分だが、あながち嘘でもない。何しろ、乾杯が焼酎ということも珍しくない土地柄だ。ソウルフードならぬソウルドリンクの焼酎にあわせて、濃い目の味つけが主流になったという。
旅の終わりに、夕暮れに染まる桜島を再度眺め、考えた。「鹿児島らしさ」とは、自分たちのアイデンティティの中に、異文化を取り入れていく柔軟性なのかもしれない。鹿児島産食材をイタリアンで表現した「鹿児島イタリアン」も、鹿児島精神の王道を行くメニューだといえる。
「東洋のナポリ」は、桜島のその姿が象徴するように、実に力強く懐の深い土地であった。